「建設業界で働いてみたいけれど、将来どうなるのか、キャリアのイメージが湧かない…」。
そんな風に感じていませんか?日々の作業に追われ、数年後も同じ「作業員」のままだったらどうしよう、という不安は、特に未経験からこの業界に飛び込む方にとっては切実な問題です。
私たち木村興業は、単なる目先の「労働力」としての“作業員”を求めているのではありません。一人ひとりが技術と誇りを持ち、将来にわたって価値を発揮し続ける「職人」へと成長できる環境を約束します。
この記事では、未経験で入社した一人の若者が、木村興業でどのようなステップを経てプロの舗装職人へと成長していくのか、その具体的なキャリアロードマップをご紹介します。
ステップ1:見習い期間(0~1年目) - すべての基礎を、身体で覚える

まず初めの一年間は、プロの職人になるための土台を築く、最も重要な期間です。
もちろん、いきなり難しい仕事を任せることはありません。最初は、現場で使う道具の名前を覚えること、安全に作業するためのルールを学ぶこと、そして何よりも「美しい仕事とは何か」を先輩の隣で見るところから始まります。
主な仕事は、現場の清掃や資材の準備といった補助的な作業ですが、これも全て「なぜ、この作業が必要なのか」を理解するための大切なプロセスです。この時期に大切なのは、スポンジのように全てを吸収し、分からないことは素直に質問する姿勢。私たちは、あなたの「なぜ?」に、何度でも丁寧に答えます。
ステップ2:熟練作業員(1~3年目) - 自分の「武器」を手に入れる

現場の流れを理解し、基本的な作業に慣れてきたら、いよいよ自分だけの「武器」、つまり専門技術を磨くフェーズに入ります。
補助作業から一歩進んで、舗装の品質を左右する「レーキ」を使ったアスファルトの均し作業など、より専門的な役割を担うようになります。
また、この時期から、会社が費用を全額負担する「資格取得支援制度」を活用し、小型のローラー(転圧機)など、簡単な重機の運転資格の取得にも挑戦します。
自分の手でできることが増え、日々の成長を実感できる、最も楽しい時期かもしれません。「指示されたから動く」のではなく、「次に何が必要か」を自分で考えて動けるようになった時、あなたはもう立派な一人前の作業員です。
ステップ3:職長・重機オペレーター(3年目~) - 現場の主役になる

経験と自信、そして資格という武器を手にしたあなたは、いよいよ現場の主役へとステップアップします。ここからは、あなたの希望や適性に合わせて、大きく二つの道に分かれていきます。
一つは、2~3人のチームをまとめる「職長」としての道。作業の段取りを考え、仲間に指示を出し、一つの工区を責任者として仕上げていきます。
もう一つは、アスファルトフィニッシャーのような大型重機を操る、専門の「重機オペレーター」としての道です。機械の特性を深く理解し、ミリ単位の精度で操作する技術は、まさに職人技です。
このレベルになると、あなたはもう単なる作業員ではなく、現場になくてはならないプロフェッショナルとして、大きな責任とやりがいを感じることができるでしょう。
ステップ4:その先の道へ(施工管理・多能工) - 自分のキャリアをデザインする
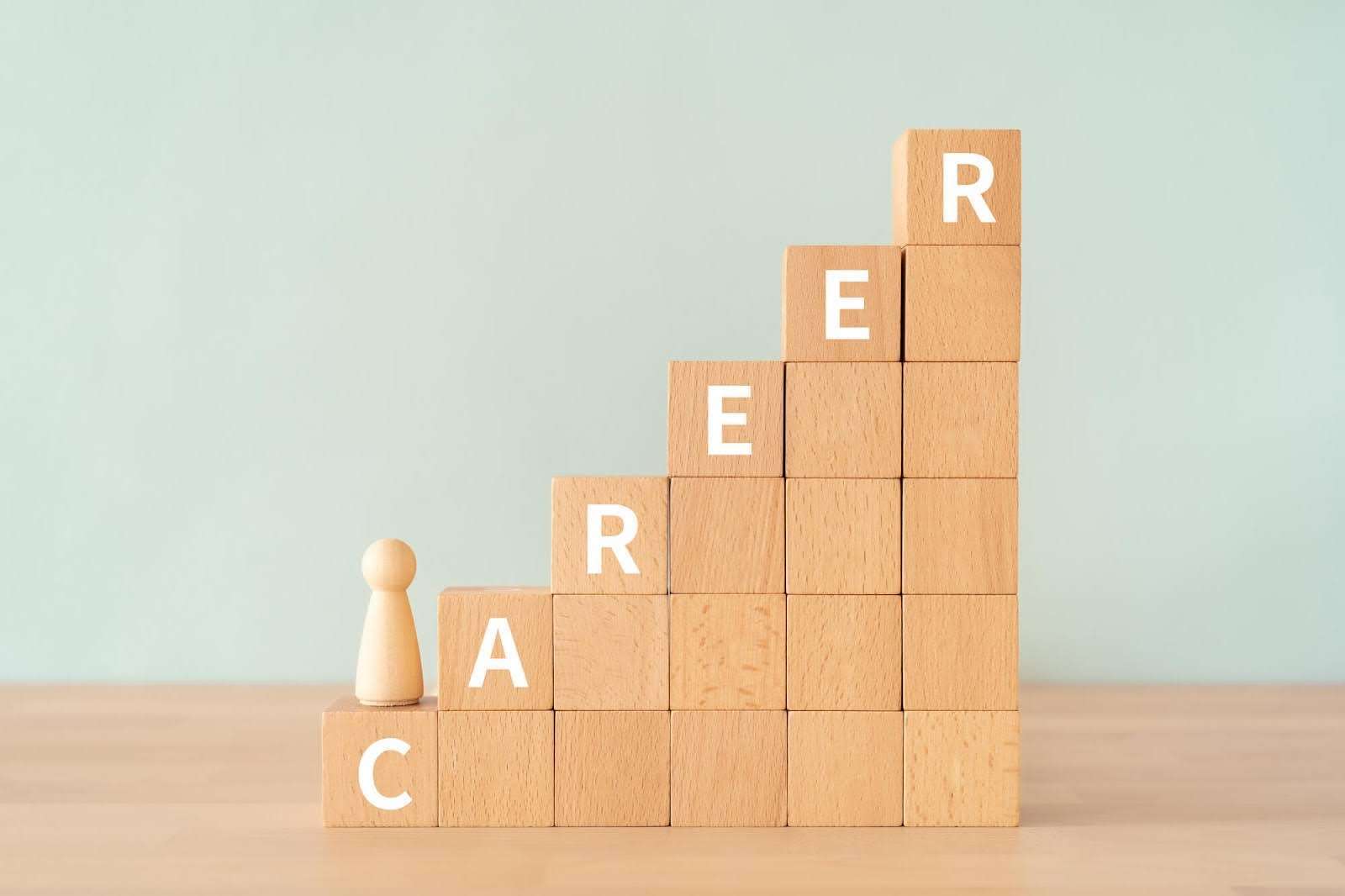
職長やオペレーターとして現場経験を積んだ後も、あなたのキャリアの道は続いていきます。
現場のプロフェッショナルとしての経験を活かし、工事全体の計画や品質、安全、予算を管理する「施工管理」への道があります。国家資格である「土木施工管理技士」の取得も、会社が全面的にバックアップします。
あるいは、マネジメントよりも現場の技術を極めたい、という想いを持つ人もいるでしょう。その場合は、舗装だけでなく、外構工事や溶接など、複数の専門技術をマスターし、どんな現場でも頼られる「多能工(マスタークラフトマン)」としての道を究めることも可能です。
私たちは、会社が一方的にキャリアを決めるのではなく、あなた自身が未来をデザインできるよう、多様な選択肢を用意しています。
このキャリアプランに、共感してくれる仲間を募集しています。
この記事でご紹介したロードマップは、私たちが、入社してくれる仲間一人ひとりに対して抱いている「成長への期待」の証です。
もしあなたが、キャリアプランが見えないまま働くのではなく、5年後、10年後の自分の姿を思い描きながら、確かな技術を身につけたいと考えているなら。
あるいは、これまでの経験を活かし、さらに職長や施工管理といった次のステップに進みたいと考えているなら。
ぜひ一度、あなたの未来について、私たちと話をしませんか。私たちは、あなたの挑戦を待っています。


